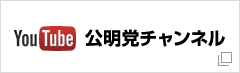2014年7月9日
集団的自衛権について読売新聞のインタビューを受ける
このほど、読売新聞静岡支局のインタビューを受け、7月9日付の読売新聞朝刊静岡版35面にその内容が掲載されました。
その大要は以下の通りです。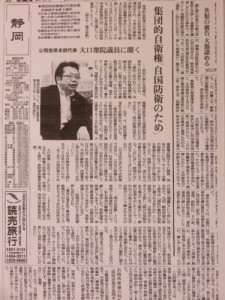 _
_
――政府の新たな見解は、従来と何が変わったのか。
「憲法上許されている、自国防衛のための自衛措置の範囲を若干、広げた。日本防衛のため、公海で活動中の米艦船が攻撃を受け、それが日本への武力攻撃の端緒、着手と判断されるかどうか紙一重のケースなどに対応できるようにした。国際法上の集団的自衛権が意味する他国防衛を目的とした攻撃が認められたのではなく、専守防衛は変わらない」
――なぜ、今、政府見解を改める必要があったのか。
「集団的自衛権を巡る従来の政府見解が出された1972年は冷戦中で、米国対ソ連という枠組みがあった。現在は弾道ミサイルや核兵器、大量破壊兵器がすでに開発、保有されている。サイバー攻撃や国際テロなど、日本に対する脅威の相手と手法に境目がなくなり、他国に対する武力攻撃をきっかけに、国の存立が脅かされる事態が起こりうる。これに対し、隙間のない対応をしなくてはいけないためだ」
「日本は日本だけでは防衛できない。(日本の防衛に不可欠な)日米同盟は、日米両国民の支持がないと維持できない。日本のために活動している米軍が攻撃を受けた時、能力があるのに日本が反撃しなければ、米国民はどう思うか。今回の解釈は、同盟強化と抑止力を高めるのにつながっていく」
――日本が戦争をする国になることは本当にないのか。
「あくまで自国防衛のための自衛の措置だという枠にははめた。当初、限定容認の新3要件は『国民の権利が根底から覆されるおそれ』という表現だったが、公明党が広すぎると主張し『明白な危険がある場合』まで限定した。解釈の限界を示したことで、これ以上の拡大は憲法の改正が必要だという歯止めをかけた」
――「明白な危険」という表現でも抽象的ではないか。
「私も党内の議論でかなり厳しく追及した。判断基準は明確じゃなきゃいけない。衆院予算委員会で、内閣法制局がきちんと答弁をし、基準を明確にすることになる」
――政権が代わると憲法解釈も変わるのか。
「憲法は基本法で最高法規。政権が代わることでころころ変わるようであれば法的安定性は崩れてしまう。政府見解はきちんとした安定性を持たなければいけない。そのためには従来の憲法解釈との論理的整合性が必要だ。新見解と72年の政府見解とは論理的整合性がある。憲法上許される自衛の措置についてのエッセンスを継承し、その中に今回の自衛の措置も収めた。そのことで憲法9条の解釈に歯止めがかかる」
――徴兵されることはないのか。
「憲法18条では『何人も、その意に反する苦役に服させられない』と定められている。憲法上、徴兵制は認められないということは自明の理だ」
――自民と与党協議をしている過程で、公明の地方議員や国民に対する説明が不十分だったという指摘もあった。
「私なりにはやってきたつもりだが、不十分だった側面は否定できない。今後は、国会での議論や広報活動などを通して国民に理解していただきたい」
- 大口よしのりについて
- 大口よしのりについて
- 活動記録
- 活動記録
- 政策・実績
- 政策・実績
- リンク集
- リンク集

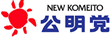








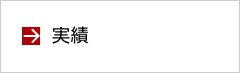 実績
実績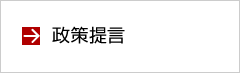 政策提言
政策提言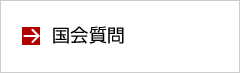 国会質問
国会質問